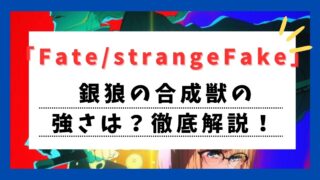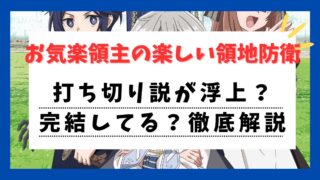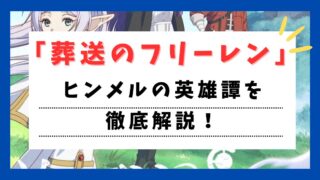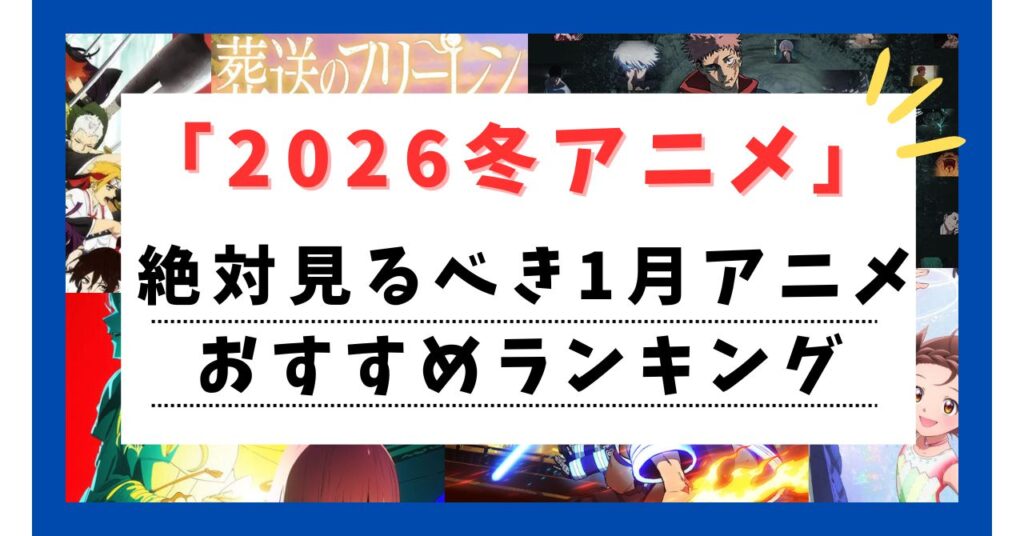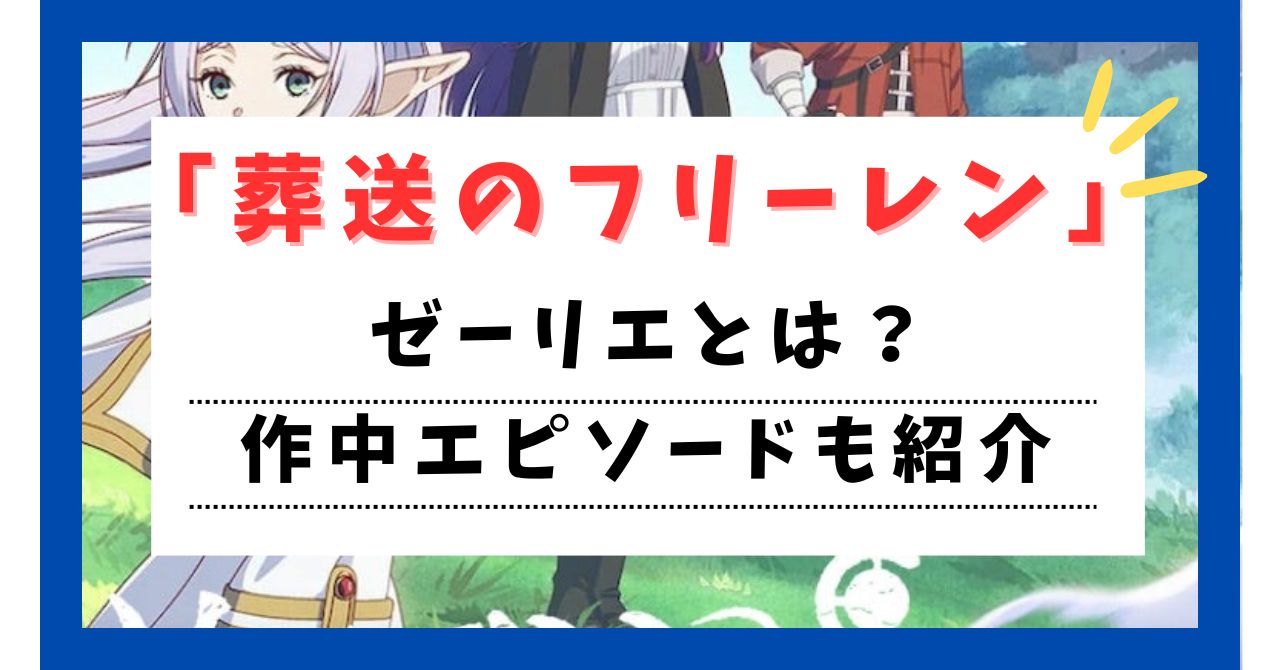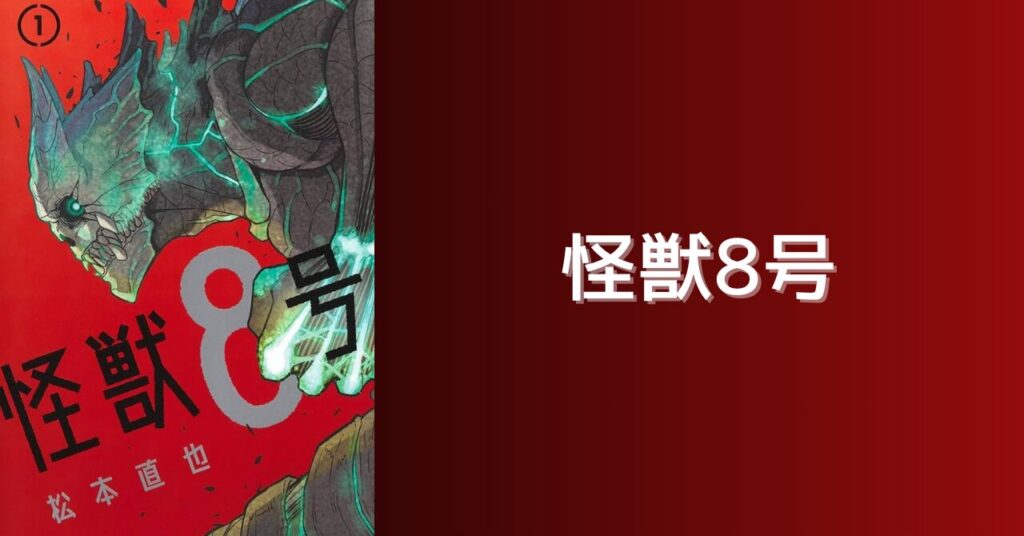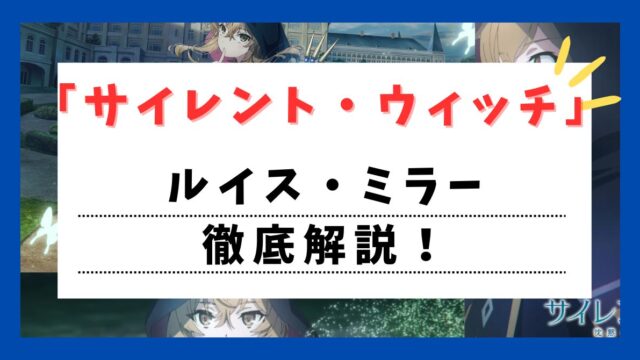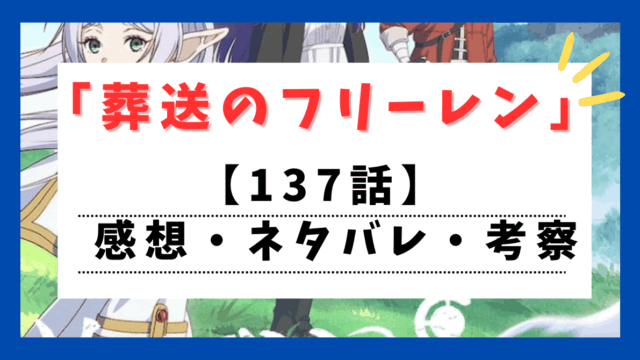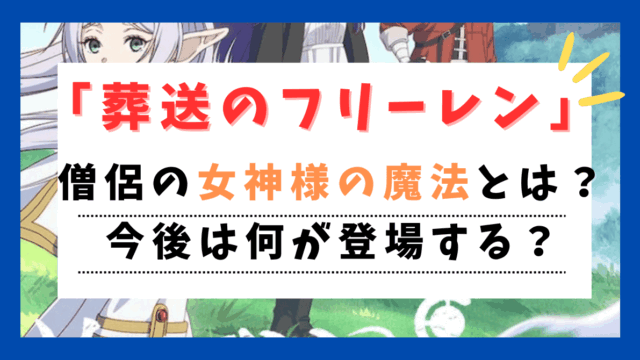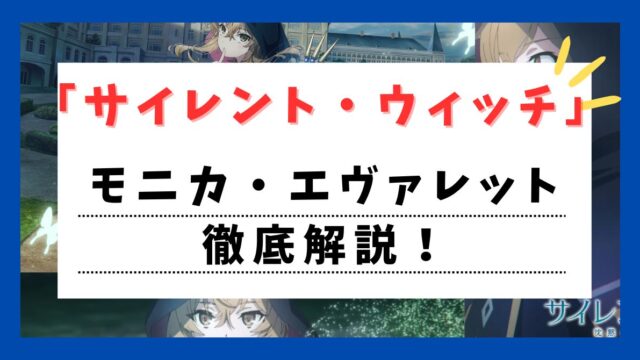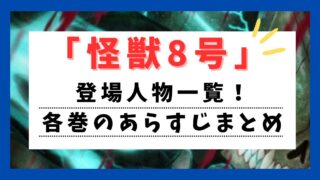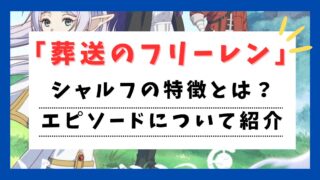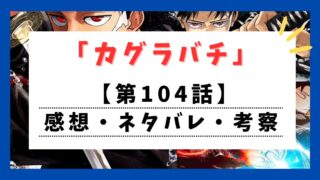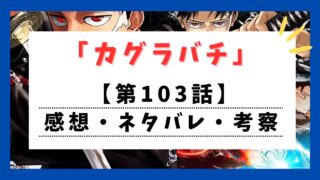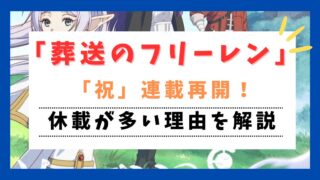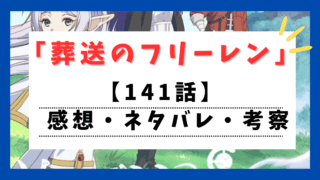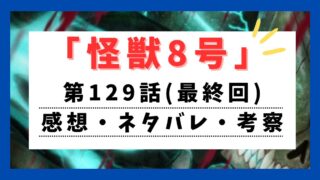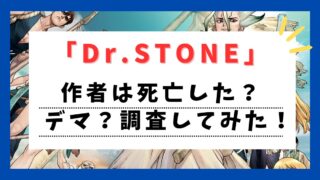『葬送のフリーレン』において、神話の時代から生き続ける存在――それが大魔法使いゼーリエです。
作品の中でも一、二を争うほどの圧倒的な力を持ち、「生ける魔道書」とまで呼ばれるゼーリエの実像は、謎と魅力に溢れています。
本記事では、ゼーリエの人物像、関係性、そして物語への影響を深く掘り下げて解説していきます。
Contents
【葬送のフリーレン】ゼーリエのプロフィール
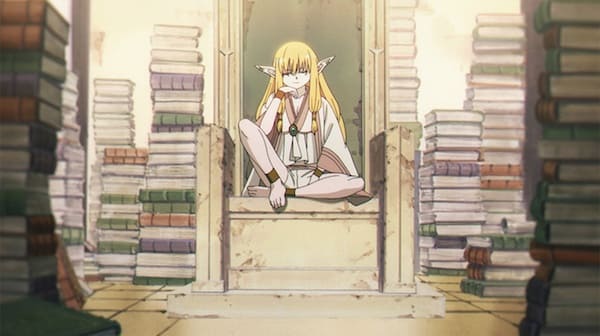 ©山田鐘人・アベツカサ/小学館
©山田鐘人・アベツカサ/小学館| 種族 | エルフ |
|---|---|
| 性格 | 好戦的で高圧的、直感で動くタイプ |
| 通称 | 「生ける魔道書」「ツンデレロリババア」 |
ゼーリエは古代から現代に至るまで生き続ける不老長寿のエルフで、エルフ特有の外見の若さに加えて、その幼女のような容姿とのギャップもキャラクター性を際立たせています。
圧倒的な魔力と知識
ゼーリエは、自ら「ほぼすべての魔道書を読破した」と語り、その知識量と魔法の理解は、歴代のどの魔法使いとも比較になりません。
彼女の弟子たちですらゼーリエの知識には追いつけず、「生ける魔道書」と称されています。
普段は魔力を制限していますが、それでも他者を圧倒するほどの魔力が自然と溢れ出しています。
一級魔法使いの試験中には、ゼーリエの魔力に怯えた受験者が失格となる描写もあるほどです。
また、ゼーリエの魔力量は魔族さえ恐れるレベルであり、魔力制御の技術も極められていて、それを見抜けたのはごく少数です。
大陸魔法協会の創設者
ゼーリエは50年前に「大陸魔法協会」を設立し、その初代代表となりました。その理由としては、以下の2つが考えられています
- 自らの寿命を悟り、知識と技術を後世に残すため
- 魔王の復活を予感し、強力な魔法使いを育てる必要があったため
この協会は、今や大陸全土に魔法秩序をもたらし、一級魔法使いなどの資格制度を通じて人類の防衛力を底上げしています。
ゼーリエの動機には表向きのものと裏の目的があるとされ、読者の間では様々な議論を呼んでいます。
【葬送のフリーレン】ゼーリエ暗殺計画編でのゼーリエの動き
ゼーリエの「予知夢」の魔法について
ゼーリエ暗殺計画編でゼーリエが「予知夢」の魔法を使えることが判明しました。
ゼーリエが使う予知夢の魔法は、「神話の時代の魔法、未来視の一種」とされています。しかし、その性質は限定的で、いくつかの制約があることが明らかになっています。
不定期かつランダムな発動
夢の中で稀に未来を体験できるものの、その時期や期間はランダムで、発動自体も極めて低い確率に左右される「使いでの悪い」魔法です。
術者の死が適用範囲
この魔法で見ることができるのは、術者が死ぬまでの未来に限られます。
そのため、ゼーリエはある時期から建国祭の最終日より先の未来を見ることができなくなり、それが自身の死を意味すると悟りました。
不完全性
ゼーリエ自身も「未来視のような大層なものではない」と述べており、完璧な未来予測とは程遠いようです。
未来を見る魔法の多くは、制限があったり不正確だったりするとゼーリエは語っています。
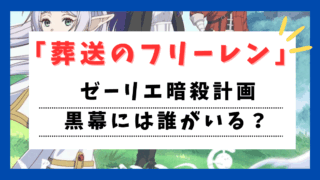
ゼーリエが観測した「死の運命」
144話で予知夢の魔法により、ゼーリエは自身の死が確定的な未来であることを知ります。
彼女が見た未来では、建国祭の舞踏会で宵の鐘が鳴る頃、死角から首を一閃されて殺されるとされています。
→144話のあらすじを読む
犯人の姿は一度も捉えられず、魔力探知にも全く反応がなかったことから、相手は「この時代にあってはならない程の手練れ」の戦士だと推測しています。
この運命を回避しようと、分身や結界などあらゆる手段を試したこともありましたが、その選択をした場合は大陸魔法協会に所属する多くの魔法使いが桁違いの規模で殺されるという、さらに悲惨な結果を招いてしまいました。
そのため、ゼーリエは弟子たちを守るために自らの死を受け入れ、舞踏会に出席するという選択をしました。
皇帝との駆け引きと「夢の接続」
ゼーリエは予知夢の中で帝国皇帝と対話し、情報交換を行います。
通常、夢の中の登場人物はゼーリエが見る夢が作り出した存在に過ぎませんが、皇帝は例外でした。
皇帝には宮廷魔法の粋を集めた精神防御機構が備わっており、それによって予知夢の中でも自我を保ち、ゼーリエと夢を繋げることができました。
皇帝はこの状況を利用し、ゼーリエ暗殺計画が自身の権限の及ばないところで動いていることを明かしつつ、帝国と大陸魔法協会の双方の利益を追求するための情報交換をゼーリエに持ちかけました。
この駆け引きの中で、皇帝はフランメが収集した「夢かどうかを判別するための魔道具」(夢の中だと火の色が黒に変わる)を使い、自分が夢の中にいることに気づいています
フランメと予知夢の魔法
ゼーリエだけでなく、彼女の弟子であるフランメも同種の魔法を使っていた可能性が高いと考察されています。
フランメが1000年後のフリーレンの行動を予測し、適切なタイミングで手記を準備できたのは、予知夢の魔法で未来を知っていたからだと考えれば納得がいきます。
フランメはフリーレンを「平和な時代の魔法使い」と呼び、「こういう魔法使いが平和な時代を切り開く」と予言していました。
これは一見すると循環論法に陥っていますが、「平和な時代の魔法使い(になったフリーレン)が未来からやってきて魔王を倒す」という、タイムリープを前提とした計画であったと解釈することもできます。
予知夢の魔法は、未来を断片的に垣間見ることができる強力な魔法ですが、その不完全さゆえに使用者を過酷な運命へと導く側面も持っています。
ゼーリエはこの魔法によって自らの死を知り、それを前提とした上で最善の未来を選択しようと苦悩しています。
一方で、フランメがこの魔法を用いて壮大な計画を立てていた可能性も示唆されており、『葬送のフリーレン』の物語の根幹に関わる重要な要素となっています。
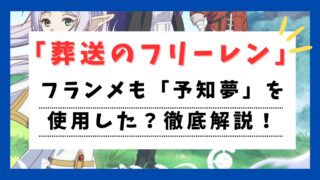
【葬送のフリーレン】ゼーリエの戦闘シーン
七崩賢マハトとの戦い
作中でゼーリエの戦闘が描かれた数少ないシーンの一つが、七崩賢の一人・マハトとの戦いです。
マハトは「黄金化」の呪いを操り、フリーレンですら敗北した強敵でしたが、ゼーリエは終始冷静に対応し、むしろ戦いを楽しむような態度を見せていました。
最終的にはマハトを封印することで決着はつきましたが、ゼーリエが本気を出していれば勝っていた可能性もあり、その実力の底知れなさを証明するエピソードです。
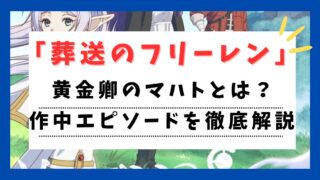
【葬送のフリーレン】ゼーリエが魔王を倒せなかった理由
性格による限界
彼女ほどの強さを持ってして、なぜ魔王を倒すことができなかったのか?
その要因は複数ありますが、最も根本的なのはゼーリエ自身の性格と魔法という力の性質にあります。
ゼーリエは、同じエルフであるフリーレンとは真逆の性格を持っています。
極めて好戦的であり、戦いそのものを楽しむ傾向がありました。彼女にとって戦うことは自己表現であり、存在意義でもあったのです。
そのため、戦いの終わり、つまり魔王討伐後に訪れる「平和な世界」に生きる自分を想像することができませんでした。
この作品の世界観では、魔法は“イメージ”の力に基づいています。
想像できないものは実現できない、という法則が支配しているのです。
ゼーリエは平和をイメージできなかったがゆえに、魔王を倒すという未来も描けず、その魔法を成し遂げることができませんでした。
技術的な時代遅れ
さらに、ゼーリエの強さの源泉は、千年前の魔法体系に基づいています。つまり、現代の進化した魔法技術からは取り残されていたのです。
例えば、かつては禁忌とされていた「クヴァールの魔法」は、現代では一般的な魔法となっています。
また、当時は一般的でなかった飛行魔法も、今では多くの魔法使いが扱う標準技術となっています。
こうした進化の中で、ゼーリエが魔族と戦っていた時代の魔法は、現代の魔王には通用しない可能性があると考えられます。
仲間の不在
加えて、ゼーリエには共に戦う「仲間」がいなかったという点も大きな違いです。
フリーレンは、ヒンメル、ハイター、アイゼンという仲間の存在によって魔王を討伐することができたと語っています。これは、個人の力だけでは成し得なかった偉業であったと強調されています。
一方でゼーリエは、圧倒的な力を持ちながらも、そうした仲間を得ることができず、孤高の魔法使いとして戦っていました。
その孤独もまた、彼女が魔王を倒せなかった大きな理由の一つだったのです。
【葬送のフリーレン】ゼーリエとフランメとの関係
ゼーリエはかつての弟子・フランメと魔法に対する理念が対立し、師弟関係ながらも激しく衝突することがありました。
- フランメ:魔法をすべての人に開放すべきだと考える理想主義者
- ゼーリエ:魔法は才能ある者にのみ授けるべきという選別主義者
理念の衝突:選別主義と理想主義
ゼーリエは、自身の哲学に基づき、才能のない者には魔法を教える意義がないと断じていました。
魔法とは本質的に特別な存在が扱うべき力であり、選ばれし者のみがその力を手にすべきという思想を貫いていたのです。
一方フランメは、魔法を万人のものとするべく努力し、誰もが扱える未来のために知識を開放しようとしていました。
彼女は、魔法が一部のエリートに独占されるべきではなく、平和と発展のために広く共有されるべきだと考えていたのです。
この両者の思想の違いは明確であり、幾度となく意見が対立し、師弟関係でありながら衝突を繰り返す要因となりました。
高く評価されていた才能
しかし、ゼーリエはそんなフランメの魔法に対する情熱と才能そのものは高く評価していました。
気まぐれで弟子に取ったとはいえ、フランメの進歩を静かに見守り続け、時には自分の考えを見直す兆しさえ見せることもありました。
ゼーリエにとって、才能があるということは何よりも重要であり、それゆえにフランメを「失敗作」と称しながらも、その業績と資質には一定の敬意を払っていたのです。
遺言書と不器用な感情表現
フランメの死後、ゼーリエのもとに届けられた遺言書を彼女は目の前で破り捨てました。
この行動は一見冷酷なように見えますが、それはゼーリエなりの不器用な愛情表現でもあります。
長い寿命を持つエルフであるゼーリエは、人との別れに慣れているはずですが、フランメという特別な存在を失ったことへの戸惑いや、割り切れない感情がその行動に現れていたと考えられます。
ゼーリエのその行動の裏には、フランメに対する複雑な感情や後悔、そしてかつて交わした数々の言葉への想いが込められていた可能性があります。
表裏一体の評価
表面上ではフランメの夢に否定的な態度を取り続けたゼーリエでしたが、内心ではその志を理解し、また彼女が人類魔法史に大きな足跡を残したことを深く認めていたことでしょう。
ゼーリエの中では、フランメに対する想いが常に葛藤として存在し、それは彼女の言動の端々ににじみ出ているのです。
【葬送のフリーレン】ゼーリエとフリーレンとの関係
真逆の魔法観
ゼーリエとフリーレンの関係は、同じエルフでありながらも魔法に対する姿勢が真逆であるという点で非常に対照的です。
ゼーリエは魔法における「強さ」や「戦い」を追求することを生きがいとしており、より強い相手との戦闘を求める性質を持っています。
一方、フリーレンは魔法に対して戦闘目的を持っておらず、「魔法は探しているときが一番楽しい」と語る探究型のスタンスを持っています。
この根本的なスタンスの違いから、過去にゼーリエはフリーレンを「この子は駄目だ」と一蹴しました。ゼーリエにとって、魔法の目的が戦いではない者は評価に値しないという明確な哲学があるためです。
評価基準の不一致
また、フリーレンは「平和な時代の魔法使い」として描かれており、ゼーリエのような戦乱の時代の魔法使いとは根本的に価値観が異なります。
このようなスタンスの相違により、ゼーリエが設けた戦闘志向の階級制度の中で、フリーレンに合格を与えることは制度的にも精神的にも矛盾していたのかもしれません。
聖杖の証の存在
特に注目すべきなのは、フリーレンが持つ「聖杖の証」の存在です。
これは遥か昔に存在した魔法協会から大魔法使いとして認められた証であり、現在の階級制度とは別の、より古くて由緒ある評価基準を示しています。
紀元前から生きているとされるゼーリエが、当時の魔法協会を率いていたと仮定すれば、正常の証を与えたのもゼーリエ本人である可能性が高いでしょう。
合格の必要性のなさ
フリーレンはゼーリエにとってフリーレンはすでに過去に認めた存在であり、現代の制度の中であらためて一級魔法使いとして合格させる必要はなかったと考えることもできます。
【葬送のフリーレン】考察記事はこちら
考察記事のリンクを張っておきます。過去の考察記事を見たい方はこちらからどうぞ。
| 135話 | 136話 | 137話 | 138話 | 139話 |
| 140話 | 141話 | 142話 | 143話 | 144話 |
| 145話 |
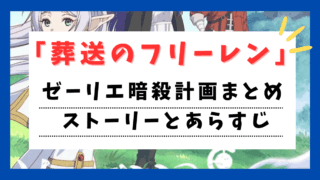
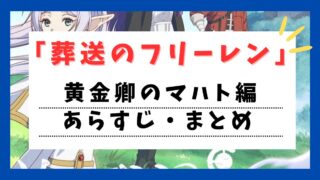
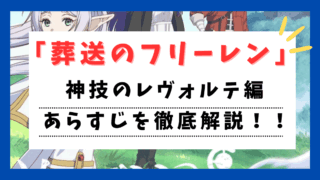
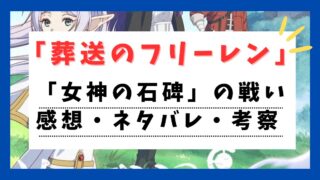
【葬送のフリーレン】キャラクター一覧
| フリーレン一行 | |
| フリーレン | フェルン |
| シュタルク | ザイン |
| 勇者一行 | |
| ヒンメル | ハイター |
| アイゼン | |
| 大陸魔法協会 | |
| ゼーリエ | ゲナウ |
| ゼンゼ | レルネン |
| デンケン | ファルシュ |
| エーレ | リネアール |
| ラヴィーネ | カンナ |
| ユーベル | ラント |
| リヒター | ヴィアベル |
| エーデル | ラオフェン |
| ブライ | シャルフ |
| メトーデ | ドゥンスト |
| レンゲ | トーン |
| タオ | ブルグ(故人) |
| 魔導特務隊 | |
| フラーゼ | カノーネ |
| ノイ | ラーガー |
| グラウ | |
| 帝国側 | |
| ラダール | 影なる戦士 |
| 魔族(七崩賢) | |
| 断頭台のアウラ | 不死なるベーゼ |
| 黄金卿のマハト | 奇跡のグラオザーム |
| その他大魔族 | |
| 無名の大魔族ソリテール | 全知のシュラハト |
| 終極の聖女トート | 神技のレヴォルテ |
| 電閃のシュレーク | 血塗られし軍神リヴァーレ |
| その他 | |
| フランメ | ミリアルデ |
| クラフト | 南の勇者 |
| シュトルツ | 大魔法使いミーヌス |
| レクテューレ | |